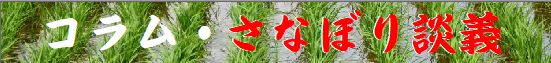
「山の笹舟」―― 平氏一門に血を享(う)けしゆえに 作 :小川 龍二
朝霧の里
女は盲(めしい)であった。
年の頃は四十を少々越えたばかりであろう。しかし、その美貌は昔に比べて少しも劣ってはおらず、却(かえ)って、今はそれに妖艶さを増して、周辺に香ばしい匂いを振りまかんばかりである。
盲と言っても、生まれ付いてのそれではない。ちょっとした不注意が元で、と云うより偶然の出来事でそうなっただけの事である。それもこの二年程前からの事であった。
「鶴様は盲になられたげな」
「鶴様じゃなか。今じゃ、ツルトミ様って呼ぶとじゃそうな。大方 椎葉での生活が苦しゅうて、眼まで潰れて仕舞うたとじゃなかろうか」
「いいや、違うとらしかばい。何でもゴマガラ(茎付きの胡麻)の取り入ればなさった時に、間違うて眼ば突いて仕舞わしたらしかと」
この女について、村人達は野良仕事の合間を見ては、勝手にそれぞれの思いを口にしていた。
鶴とかツルトミとか呼ばれたこの女が、九州の奥深い山里 日向国(ひゅうがのくに)椎葉(しいば)から、椎葉に比べればやや平地の多いこの肥後国(ひごのくに)求麻(くま)(球磨)の里 宮原村(みやのはるむら)に戻って来たのは、この一ト月程前の晩夏の頃である。
十三歳でこの里を出て、三十余年振りの帰還であった。
求麻の里一帯、此処(ここ)宮原村も霧が多い。晩秋の早朝などのその深さは、僅か五・六間(約9~10メートル)先さえも模糊として物の形として分かる程度で、行き交う村人の顔もよほど近付かぬ限り判別できぬ程である。往還を一町(約109メートル)も早足で進めば、霧の所為(せい)で自慢の髪も眉の毛も真っ白に変化するであろう。盆地である地形の昼夜の気温差と、此処から一里半(約6キロメートル)程離れているが、盆地の中央を悠々と流れる清流求麻(球磨)川の水温の変化、これらがこの里まで作用するのかと、今更ながら人々は自然の営みに驚嘆するのであった。
「おばば様はもう起きなさったであろうか」
ツルトミと呼ばれた女は衝立に手を掛けて、裏の様子を窺(うかが)った。特に物音はしない。
東の山の端からは、やわらかい秋の陽射しが徐々に縁側から奥の方にも忍び寄り始めた。深い霧に閉ざされていた地上の万物は、時間の流れとともにおもむろにその姿を露呈し、今は精一杯己の勇姿を誇示せんとしている。
「目が見えぬのが口惜(くちお)しい。じゃが、今更(いまさら)悔いても詮(せん)無き事」
女はそう己に言い聞かせ、後ろに廻った。
様子がおかしい。
「おばば様」
声を掛ける女に、床に就いている筈の老女は「ウーッ」と呻き声に似た声を上げた。夜具の上に座している様子である。
「もしや、またも……。」
見えぬ目で手探りしながら、女は夜具の中に手を入れた。
やはり……、夜具はびっしょりと濡れそぼっている。
「おばば様、早う」
女は急いで襦袢と腰巻を脱がせ、傍(そば)にあった別の襦袢を羽織らせた。一体 何が起きたのか、老女は一向(いっこう)分かたぬ風である。否、たとい分かっていたにしても、もう四半刻(しはんとき)(30分)も経(た)てばすっかり忘れて仕舞うことであろう。
女は遣戸(やりど)を開け放って、新鮮な朝の空気を老女の寝間(ねま)に取り込み、僅かなりとも部屋に立ち込めている臭いを消そうとした。この老女は女の養母(はは)であり、名をトミと云う。
濡れた夜具は縁側に乾そうと思うが、じっとり小水を含んだそれは重い。急いで運ぼうとすると、女はいま開けたばかりの遣戸の角に、目から火が出るほど右側面を当てて仕舞った。
その騒がしい物音に驚いて、手水場(ちょうずば)から養父(ちち)宮原(みやはら)親重(ちかしげ)が不自由な足で飛んで来た。
「済まぬのう。そなたには何時(いつ)も面倒ばかり掛けておる」
彼は女から夜具を預かり、縁側から更に外の物干し台へと夜具を掛けた。
話は一気に三十数年前まで遡(さかのぼ)る。
当主宮原親重(ちかしげ)の住まうこの宮原家は、数代前から続く付近一帯の小領主の家柄であった。屋敷も広大な構えで、分限者(ぶげんしゃ)中の分限者と云えた。まだ、兵農も分離していない時代の事である。一旦事が生ずれば、先代も親重も農兵の郎党を引き連れて戦(いくさ)に馳せ参じるのを常とした。
先の文治元年(1185)、平氏を討滅して鎌倉に幕府を開いた源頼朝は、守護・地頭の任命権を獲得して、この宮原村から程近い肥後国求麻郡(くまごおり)多良木荘(たらきしょう)には遠江国(とおとうみのくに)より相良頼景(さがらよりかげ)を封じた。後の建久三年(1192)には、頼朝は征夷大将軍にも叙任された。
平氏が壇ノ浦に滅亡してより、まだ数年しか経っていない時期の事である。時代の流れには抗し難く、宮原家も勢い相良氏の被官となるに及んだ。
平家残党の探索も決して緩んだどころではなく、むしろ一層その厳しさを増していると云って良い。残党のその大多数は峻険な山中に逃れ、源氏の追捕(ついぶ)の手から必死に身を護らんとしていたのである。
此処(ここ)多良木荘の相良氏は、かつて遠江国相良荘にあった頃、本来平氏の与党であった。その経緯から平家残党の追討の下知には当初冷淡であったが、源氏の寄騎(よりき)となった今、頼朝の命に背く事など出来る筈がない。
その相良氏の被官たる宮原家にも、時代の余波は容赦なく襲って来ていた。
或る夜の事である。
宮原家の当主親重は妻トミに何時(いつ)とはなくしみじみ話し掛けてきた。柔和な中にも厳格さを併せ持つその面上には、滅多に見せぬ苦渋の色がありありと見て取れる。更にその横顔を照らす灯は、彼の秀でた額と鼻梁の陰翳(いんえい)を一層際立たせて、より以上に苦悶の様相を色濃く滲ませているのである。
「鶴が事じゃが、もうわしらでは如何(いかん)ともし難き仕儀(しぎ)に相成りたる様じゃ」
「はて、お前様。如何ともし難きとは? 鶴が如何(いか)なる事にござりまするか」
トミの怪訝(けげん)そうな顔付きは、まるで親重を睨(ね)めつける様なそれになった。
「その事ぞ。トミ。そなたも既に聞き及んでおろう、鎌倉殿の討手(うって)が 近年この付近にまで及びおると云う専(もっぱ)らの噂じゃが……。鶴はわしらが可愛(もぞ)か子ぞ。なれど、不憫じゃが、鶴を、何処(どこ)ぞへなりと匿(かく)もうて遣らねばなるまいぞ」
「匿うとは? また、何故に?」
トミは合点が行かぬと云う顔をして、親重に問い返している。親重は続けて、
「あの子がまだ物心付かぬ頃、一人の雲水から預かりて今日まで育て来たるが、事が露見する前にじゃ、何処ぞへ匿まわねばならぬと思う。近辺を嗅ぎ回れる不審の輩(やから)が、この頃少なからずとの噂じゃ。そなたも覚えておろう、あの折の旅路の僧の話し。雲水殿は、『所要で日向の国鵜戸(うど)まで行かねばならねど、途上で妻(さい)を亡くし困(こう)じ果ててござる。どうかこの児を一時(いっとき)お預かり下されまいか。何れまた引き取りに参りし折りに、お礼はたんと致したき所存なれば……。身共の名はご容赦あれ。この児は年端も行かぬ赤子なれど、名をつると称しておりまする』と申せしが、わしが見る処、かの僧は、あれは平家の落武者じゃ。身なりこそ乞食(こつじき)に窶(やつ)してあれど、かの風貌は唯(ただ)の家人(けにん)にはあらじ。多分に名のある武人ぞ。それに鶴を包(くる)んでありし かの布は、あれは平家の赤旗に相違なし。また、別の供の者が、小声でカゲキヨ様とも呼ばわっておった」
一息ついて、親重は再び話を続けた。
「先だって、鵜戸の社(やしろ)に詣(もう)でし者があってのう。その者の話じゃと、先年鵜戸の社前に於きて、否、他の社前のことやも知れぬが、己の目玉を刳(く)り抜き自害し果てたる武人のありし由。その武人は、名を悪七兵衛 平景清(あくしちひょうえ たいらのかげきよ)とか称せし仁(じん)なるらし。臨終(いまわ)の際(きわ)まで、肥後に残せし娘こそ気掛かりなれ、と 宣(のたも)うてありしそうな。故に……」
と、更に言葉を接(つ)ごうとしていると、親重の脇の灯火の油が無くなったのであろう、今までジーッと虫の音の様な音を立てて燃えていた灯が、急に細くなった。細くなると同時に、一匹の蛾が何処からか勢いよく飛び込んで来て、二・三度うるさくその灯の周りを飛び回っていたかと思うと、一気にその灯を吹き消して仕舞った。
トミが油を継ぎ足しに行っている暫くの間、親重は腕組みをした儘(まま)もう一点の灯火(ひ)に目を転じた。身じろぎひとつせず黙想する彼のその後ろには、大きな黒い影がゆらゆらと揺らめいている。その黒い影が夜の重苦しい沈黙を一層際立たせていた。
やがてトミが戻り、再び元の座に坐り直した。
「十二まで育ててのう。されどお前様、鶴は女子(おなご)じゃ。十二まで育てて、これから娘盛りじゃと云うに。それをみすみす……。思うに、源氏は女子にも害をなしまするか。それに私共も、もう若くはありませんぞ。既に老いの坂じゃ。私は嫌じゃ。私に本当の子でもあらば兎も角(ともかく)……。これから如何(どう)なさるのじゃ。行く行くは鶴に婿を迎え、孫の姿を見て安穏に過ごさんと思うて居りしに」
「鶴が為なれば……。増してや、平氏の縁(えにし)の者なれば、源氏にとりて男も女子もあるまいぞ。いつ何時捕縛に参るか分からぬのじゃ」
と、言いつつも親重は、今に泣き出さんばかりに首を横に振るトミの姿に、もう言葉を接ぐ気力も失って仕舞った。「嫌じゃ、嫌じゃ」とトミは先程から繰言を述べるばかりである。
その様なトミの姿に、もうこれ以上の話は無闇に彼女を錯乱させるばかりであろうと親重は考えた。何か物言いたげなトミを遮り、
「もう、今夜も遅か。話はこれまでじゃ。続きはまた、改めて後日……」
一言二言そう言うなり、黙りこくってその儘そこに横になった。トミが話し掛けても、もう返事もしない。鶴とトミはそれぞれの寝間に戻った。
ややあって全てを闇が包んだが、トミは遅くまで寝付けぬ様子であった。
宮原親重に子はなかった。一人だけ生まれるには生まれたのだが、襁(むつき)も取れぬ儘に夭逝(ようせい)した。女児で、名を「芳(よし)」と云った。
それだけに、旅僧が赤い布切れに包んだこの子を連れてきた時には、これぞ天の恵みとばかり、トミと一緒に喜んだ。雲水は幼子の名を「つる」と呼んだ。その「つる」に「鶴」の字を当てて、二人の養親は鶴、鶴と呼んで可愛がってきたのである。
鶴は成長するに従って美しさと華やかさを増し、その利発さにおいても村の子供らに一層抜きん出ていた。
「やはり貴人の血は争えぬ」
親重には、カゲキヨと呼ばれた雲水と、その雲水が持参した赤旗一旈(いちりゅう)と小太刀一口(ひとふり)に思いを巡らす度に、そう思えた。否、近頃では間違いなく貴人だと信じている。
であればこそ、たとい女であっても平氏の血を享(う)けし者を、源氏の輩(やから)は決して赦す事はないであろう。何しろ源氏の棟梁は、猜疑深く非情で冷酷との評判の高い頼朝の事である。つい先頃は奥州の地に舎弟義経を討ち、その忘れ形見さえも誅(ちゅう)する程の過酷さなのであった。
思えば鶴がこの家に来て以来の二人の養親にとっては、この上ない幸せな日々であった。しかし、その娘を嫁にではなく、他家に、それも密かに出さねばならぬとは……。嫁に出せしものにあらば、時に相見(まみ)える事も出来ようと云うもの。だが……、と考えれば考えるほど二人にとって、鶴が不憫で哀れに思われてならなかった。
此処宮原村は肥沃な土地柄であった。穀類も野菜もふんだんに獲れた。
裏山に登れば、春には筍、蕨、土筆と様々な物が豊富で、鶴は幼い足で親重やトミに付いて回った。秋には柿、栗と果実も潤沢である。また、近くを流れる溝からは鮒、鯰、泥鰌(どじょう)など、時には鰻も良く取れた。屋敷の池には鯉も泳いでいた。
鶴は屈託なく笑い、遊びつつ成長し、一方では詩文も書も驚くほど良く学んだ。
更には貴人の血を失わせてはならぬと、親重は 己の知る限りの知識や礼儀作法、都に云う有職(ゆうそく)故実(こじつ)と呼ばれるものをさえ、惜しげもなく、まだ幼いとも思える彼女に授けたのである。言葉遣いでさえ、可能な限り都言葉を使用させんとした。
その厳しい躾にも耐えてよくぞここまで、と親重は今しみじみと思う。
村の子等は己の父母を「父(とと)しゃん、母(かか)しゃん」と呼んだが、この家は「父様、母様」である。宮原家は村の子等にとって、真に奇怪な家であった。言葉遣いも行儀作法も、日常の生活の全てに亘って、彼らとはまるで異なるのである。その子らも歳を重ねるに従って、己らとは何かが違うのだと、おぼろ気ながらも意識し始めている。
十一の時、鶴は初潮を迎えた。体つきは丸みを帯びて肌理(きめ)細やかな肌となり、禿(かぶろ)は豊かな黒髪となった。その黒髪が微風(そよかぜ)に靡(なび)く頃になれば、鶴の何気ない立ち居振る舞いの一つひとつまでが、一層艶めかしく匂う様に思われるのである。
何時の間にか成長した娘の姿に、親の親重さえドキッとする様な趣である。彼自身が戸惑う事もしばしばであった。その様な時の親重は決まって、父祖伝来の太刀や武具を異常と思えるほど丁寧に手入れした。そうして、気分一新するのを常とした。
宮原家の家人(けにん)茂吉(もきち)が家に、茂助(もすけ)と云う鶴より二歳(ふたつ)ばかり年上の男児がいた。鶴の幼少の頃、茂助は常に彼女の傍にいて良く笑わせた。万一鶴に誰か悪戯(いたずら)でもしようものなら、茂助はその全身に怒りを表わし、その者が泣き出すまで殴打した。
「茂助は鶴が好きなのじゃ」
と悪童どもは囃(はや)したてて面白がったが、その様な悪童共を、茂助は我を忘れて何処までも追い駆けて行くのである。
その茂助が、近頃鶴に話し掛けようともしない。むしろ、意識的に避けている様子である。ではあるが、鶴は何処かに茂助の目を何時も感じていた。やや離れた場所から、或いは鶴の見る夢の中でさえ、茂助の目が常に己を追っている思いである。
であればこそ、鶴から先に話し掛ける事は一層躊躇(ためら)われた。近頃では彼女の心の内にも、今までと異なる何か得体の知れぬ新しい変化が生じつつあった。これが大人になる事であろうかとも思うが、己もはっきりとは認識できない儘である。だが、茂助の行為は、鶴にとって決して悪い気はしない。むしろ始めて味わう えも言われぬ心地良さであった。
その様な中、鶴を取り巻く多くの悪童連中は、徐々に彼女の周りから離れて行く様になった。それは鶴が彼らにとって、年々近寄り難い存在になって来た所為(せい)でもあったろう。否、むしろ十二・三も過ぎた彼らは既に一人前の働き手として、遊び呆けている余裕もない状況にあったのである。
ただ茂助だけはそれらに増して、己に対しては親切以上の或る深い大人の感情が、其処かしこに見え隠れしている様子なのである。その様な態度の茂助に接する時、時には彼に対し、思春期の女の性(さが)か嫌悪感さえ覚えた。しかし通常は、或る優越感以上の支配者にも似た思いで、この男を眺めている己のほうが多かった。これは新しい発見であった。時にはそう云う己の思いを卑しいと考える余裕さえ、この成長した少女に生じせしめていたのである。
近頃、鶴と同じ年頃の娘の多くは、近在の分限者の働き女(め)となり、或いはまた商家の奉公人となっている。事実、この宮原家に於いてさえ、鶴の幼馴染が住み込みの下女として奉公に上って来た。そうではなくとも、貧乏所帯の子守や飯炊きの手伝いは、幼い頃からの彼女らの仕事でもあった。時には、いつの間にか姿が見られなくなった娘もある。口減らしのために、密かに身売りされていたのである。
然るに、ひとり鶴だけは他の者と異なる裕福な境遇の中にあった。それ故に、他の同じ年頃の娘達の日焼けた顔と荒れた手を見るにつけ、或いはまた痩せ細った体の少女らと行き会う時、鶴はこそこそ身を隠したい思いにさえにも駆られた。
中には小さいながらも不治の病を背負い、楽しい夢さえ見る事なく世を去った子供も決して少なくはない。その様な運命を背負った子供らに接する時、もう居たたまれない思いがして、鶴は己の所為ででもあるかの様な哀しい気持ちであった。
「私も何かをせねば。母(かか)様のお為になる事を。何かお手伝いでもせねば相済まぬ事じゃ」
その様には思う。が、何をどの様にすれば良いのか判らない。
武家の娘として、父親重も母トミも学問や礼儀作法の他にも書、裁縫、生け花等一通り以上の教育を施してはきた。そればかりではない。例え女性(にょしょう)とて武芸の嗜(たしな)みがなくてはならぬ、と親重は鶴に厳しく仕込んだのである。
一方、多良木荘に遠江より下向した相良頼景とて、まだ安泰ではない。頼景が嫡男長頼(ながより)は鎌倉の頼朝の命を受け、人吉の豪族矢瀬(やぜ)主馬佐(しゅめのすけ)を胸川(むねかわ)(求麻川支流)に討たんとしている。頼景に遅れる事約五年、長頼は父頼景同様に頼朝から人吉荘の地頭として任じられていたのである。
親重は思う。増してや鶴は源氏の宿敵、平氏の流れではないか。何が起きようとも不思議はない。実子ではないが、永年手塩に掛けて育んできた娘である。その愛娘を、いかなれば源氏の手に委ねられよう。親重の不安は日毎に募って(つのって)いった。
数十町歩の山林と田畑は、普段は家人に小作をさせてはいる。であるが、いざ鎌倉と云う段に於いては、一族郎党を束ねて相良の寄騎として戦場にも馳せ参じなければならぬ。だが、平氏の息の懸かった者は、何人たりと雖(いえど)も生かしておかぬのが頼朝である。その流れなれば尚の事、この先不測の事態が起きぬと何ゆえに断言出来ようか。
「油断はならぬ」
あれこれに思いを馳せていた親重は、思わず自分でも吃驚(びっくり)する程の声を出して仕舞った。その声に、庭の隅で転寝(うたたね)をしていた野良猫が驚いて頭をもたげ、頻りとこちらの様子を窺っている。何時でも逃げられる様、警戒しての眼差しであった。
時は巡り、厳しい冬も眼前に迫る頃となっていた。
旧暦霜月の朝は、宮原村においては文字通りの霜の月である。眩いばかりの朝日を浴びて、麦畑の霜柱がキラキラと輝く。働き者の百姓達は、もう麦踏みの作業に出た様だ。
朝餉を終えて庭の中を一回りしてきた親重は、下女に命じてトミと鶴を座敷に呼ぶべく申し付けた。
間もなくして、二人は床の間を背にした親重の前に畏(かしこ)まった。二十畳ほどの比較的大きな部屋である。沈痛な面持ちの彼の姿に、主(あるじ)殿のこの様な渋面は、彼が二度ばかり戦場に出た時以来ではないか、とトミは思う。
徐(おもむろ)に親重は口を開いた。低い声である。
「のう、鶴。よう聞いては呉れぬか」
親重はごくりと唾を飲み込んで、また続けた。
「そなたも薄々気付いてはおろう。そなたはこのわしの、宮原家の真(まこと)の児にはあらず。そなたの真の父御(ててご)は……」
親重は己の瞼の裏に熱い物を感じながら、これから先の事を言うて聞かせねばならぬ、とやや気負いながらも躊躇した。
「そなたの真の父御は、多分に平家の名のある武士(もののふ)ぞ。わしが察するに悪七兵衛 平景清(あくしちひょうえ たいらのかげきよ)様と思うておる。壇ノ浦の合戦に、あるいは屋島の合戦にと目覚しきお働きも虚しく、戦に敗れ、武者共と共に各地に逃れたもうたのじゃ。平氏の落人の或る者は久連子(くれこ)や樅木(もみき)へ、或る者は五木へ、また或る者は日向の椎葉へと身を隠し、いや、遠くは四国へ逃れし者もあると云うぞ。さて、かの景清殿が事じゃ。風聞じゃと景清殿は日向国鵜戸へ逃れたもうたにや申す。されど、生死の程は今も分かたぬ。今は昔の事なれど、そなたがまだ乳飲み児なる時分の事じゃ、夏の暑い晩じゃった。案内(あない)を乞う物音に出てみれば、言うては何じゃが、一人の乞食僧が赤子を抱きて立ちておる。話を聞けば、妻に先立たれて難渋致しおる由。また供の者共も、幾多の山々を越ゆる内、何時しか離れ離れになりにけり、との申し条じゃ。旅の疲れもあるべしと、湯茶なども勧めしが、先を急ぐ事なればこの赤子をこそお預かり下され、との申し分なれ。行く先は日向の鵜戸とも……。名は明かされねどとて、差し出(いだ)だしたる小太刀一口(ひとふり)と赤子を包(くる)みし赤旗。幸いなるかな、トミは吾が児を亡くし悲しみ塞ぐ日々なれば、そなたを引き取り育つる仕儀に相成った。茂吉を除き村の皆の者には、鶴は、トミが遠縁椎葉家からの貰い児じゃ、と言うておいたのじゃ」
此処(ここ)まで話すと、彼は目の前の茶に手を伸べて、ゴクッと一息に飲み乾した。更にまた話を続けた。
「されど、鶴。近年のこの近辺の騒々しさ、そなたも存じておろう。戦もまた 何時(いつ)始まるやも分かたぬ。増してや鎌倉殿の平家残党の探索は、これまた日に日に厳しくならんと云う専ら(もっぱ)の噂じゃ。そなたが平氏の流れを享くる者と、いつ何時露見せざるとも限らぬ。人吉にはその下知を承(う)けし者もたんと居るげな。ゆめゆめ油断はならぬ。そこでわしの思案なれど、一旦 日向国・椎葉に身を隠さば如何(いかが)ならん。幸いにして、椎葉の里の椎葉家は母様が縁続きぞ。十二の身で不憫じゃが、一時(いっとき) 向こうに身を隠しては呉れまいか」
親重の顔は歪み、時折声を詰まらせた。
トミはと云うと、何時ぞやの夜 親重からそれとなくその話を聞いて以来、やがてはこの日が来るとは思うていたが、袖で目を覆った儘で肩は小刻みに震わしている。
晩秋の空は完全に晴れて、もう外の霜は跡形もなく消え去っているのであろう。閉め切った障子には、枝振りの良い松が影を落としている。
先程から、鶴は押し黙った儘である。口を開いて何かを問わんとするが、全てをその場の重苦しい空気が押し殺して仕舞う。椎葉に身を隠さば如何(いかん)、との親重の問い掛けながら、彼の胸の内では既にその方向で決している事であろう。娘に説き聞かせねばならぬ養父(ちち)のその心の内を慮る時、鶴にはそれに抗う理由など何ひとつ見出せなかった。少女は紅い唇(くち)を震わせ、やっとの事で親重に問い掛けた。
「父(とと)様、椎葉とは、椎葉とは如何(いか)なる処にござりまするか」
その程度の問いしか、今は浮かんでこないのである。
「左様じゃな。その椎葉なるは、此処宮原村より十五・六里(約60キロメートル)もあろうて。幾つも幾つも険しき山道を越えねばならぬ。山道とは云うても、云わば岨道(そばみち)と獣道だけじゃ。滅多に人も踏み込めぬ処じゃて……。このわしも四・五度行きし事あれど、大の男さえ道中難儀する処なれば、とても冬の間など踏み込める場所にはあらざる。されば身を隠さんと思えば、この上なき処。良かか、鶴。椎葉には平家の落人も数多(あまた)隠れ棲(す)むとも伝え聞く。その数二・三十人じゃそうな。中にはそなたの父御(ててご)の消息を知る者があるやも知れぬ。いいや、そなたの父御景清殿の供の者さえ居るかも判らぬのじゃ。かの雲水殿は、山中にて供の者とも離れ離れになりけると、言うておわせしぞ。壇ノ浦からの逃避は山から山への連続なれば、かかる事十分あり得べし」
鶴は俯(うつむ)いた儘黙っている。しかし、時とともにその双眸は潤み、やがて雫(しずく)がポトリと落ちた。
「例の物を」
ややあって、親重がトミに言う。トミは暫く動こうとはしなかったが、不承不承の体(てい)で涙を拭きつつ席を立った。
程なくトミが持参した物は、小太刀と小さく折り畳まれた赤い布切れである。布切れは折り畳んだ端々が既に破れ掛かっていて、赤い色はむしろ黒ずんで見えた。
「これがそなたを預かりし折、雲水殿が手向けたる小太刀じゃ。なかなかの業物(わざもの)と見ゆる。またこの赤き布切れは、正(まさ)しく平家の幟(のぼり)に相違あらじ。そなたの赤子の時分、そなたはこの旗に包まれてありき」
親重は、己の膝の前に出されていた二度目の湯茶に手を出した。美味しそうにひと飲みしてから障子を開けさせ、新鮮な朝の空気を座敷に取り入れた。
その開け放たれた障子から外に目を移すと、この夏以来何時の間に植わったのかは知らぬが、盛りをとっくに過ぎた薄(すすき)の白い穂が、吹く風に任せて右左と思う儘に揺れている。
親重は言葉を継ぐ。
「出立は、そうじゃ、早か方が良かろう。これからは雪も深こうならん。春となって雪も溶ける頃には直ぐに……。それまでは、母(かか)様にせいぜい孝養致せ」
話を終えると、親重は鶴から障子の外に目を遣った。やはり庭の薄でも見ているのであろうか。ただ、これまで胸に支えていた物を全て吐き出して、幾分安堵したものでもあろう。先ほどまでの歪んでいた顔の表情から、何時の間にか、鶴の知るついこの間までの穏やかなそれに戻っている。
そして時を経ずして養父は、そそくさと畑の見回りに出かけて仕舞った。
その夜、母子はひとつの部屋に床を取った。
鶴は昼間どのように過ごしたのか良く覚えていない。大方 すぐ裏の山々や、近くの宮原神社の方を眺めながら一日を過ごしたのであろう。
二つの床の中で、鶴はトミの方を見遣った。今まで気付く事もなかったが、薄暗い火影の中でさえ、トミの髪には何時の間にか白いものが多くなっている様に思われた。顔の皺(しわ)も相当増えた様だ。
「孝養せねば…。此処に居るこの冬の間だけでも」
だが、何をどのようにして孝養すればいいのであろう、そう思いつつ鶴は目を閉じた。閉じた瞼からは止め処(ど)なく涙が溢れてくる。
その時、眠っていると思っていたトミがポツリと言った。
「そうじゃ。そなた、椎葉に行かば、呼び名をツルトミと呼ばわっては呉れまいか。そうじゃ、鶴富が良か。私は、そなたと何時も一緒じゃ。そなたも、時には私が事も思い起こして呉れようぞ。そうじゃ、そうじゃ。そいが良か」
黙っていたかと思うと、或る事を思い出してはまた話す。二人はその日、夜半を過ぎてもなかなか寝付けなかった。
その年の冬は例年にない大雪であった。
遠望する市房の山も、近くの黒原山も上から下まで真っ白である。宮原村の親重が屋敷はこの黒原山の麓にあるが、此処から多良木盆地の方を眺めれば、これまた一面 白を塗り潰したような世界である。裏庭では椿の花も今盛んであるが、枝葉から五・六輪がスッポリと抜け落ち、白い大地に鮮やかな赤い色を映じていた。
幕の内も過ぎたというのに、今年はさっぱり梅の便りも聞こえて来ない。雪だけは多い。
彼は、時折 黒肥地に構えた相良の館に出仕する。黒肥地は多良木とは求麻川を挟んだ隣村に位置する。天然要塞の地と云って良い。この大河を目の前にした地に、遠江から下向した相良頼景は約四十五間(約80メートル)四方の館を営んでいたのである。
親重は無理に出仕する必要もないのであるが、この日も一刻(いっとき)(2時間)の時間を掛けて雪の中を押して行く事にした。途上で深い雪に足を取られ、喘ぐように吐く息も白い。親重の目的は、此処に隠居する頼景へのご機嫌伺いと、頼景が嫡男長頼の人吉城入城を賀し、併せて鎌倉の平家残党追捕の推移をそれとなく探らんが為である。
あれこれと頭の中を整理しつつも凍える様な手足をして、程なくして親重は黒肥地の入り口に着いた。
晴れた日であれば、此処からも東に市房山、南の方角に白髪岳(しらがだけ)や黒原山が望めるのであるが、先程から再び雪が激しくなって今は何も見えない。求麻川の川原も白く覆われていて、所どころに長く枯れた薄(すすき)や僅かな潅木(かんぼく)が雪の上に顔を覗かせているばかりである。ただ、水は一部を除いて凍ることなく、人吉方面の下流に向って流れていた。
親重は頼景の前に膝行(しっこう)した。機嫌は良かった。真っ白な銀世界が、やはりこの猛者の心をも洗ったのであろうか。暫くの間最近の人吉の情勢、少々早い事ながら今年の収穫予想など話し合っていたが、その後 突然頼景がこう切り出した。
「時に、親重殿には才気溢(あふ)るる美貌の娘御があると聞く」
何時 頼景は鶴が事を知ったのであろう。鶴が平氏の流れなる事も知った上での話であろうかと、親重は内心たじろぎ、少々うろたえる思いであった。
「如何じゃ。わしが嫡男長頼にもそろそろ妻女を娶(めと)らねばならぬと思うておる。親重殿、そちが娘御は如何ぞ」
「いやいや、お館(やかた)様。滅相もござりませぬ。吾が娘なぞ、その付近の村娘にござりまする。それに勿体なくもお家の家格がまるで違いましょうぞ。嫁取りと申さるるにあれば、上村様にもよき娘御がお有りと聞き及んでおりまするが……」
「上村か」
頼景は傍の火鉢に手を炙(あぶ)りながら、ちょっと思案している様子である。上村家は宮原村から一里程の、やはりこの付近の山岳白髪岳の麓に位置する小領主であり、相良家の執事となる家柄である。
親重は、鶴の話題を頼景から逸(そ)らすのに必死であった。権門の違いを盾に、頼景が申し出を体よく断わらんとしている。やや時を置いて話しを転じ、鎌倉の動静を頼景に尋ねた。
「まあ、よい。上村が娘の事は考えておこう。時に鎌倉殿は、開幕以来破竹の勢いじゃ。先に奥州にありては舎弟義経(よしつね)殿を討ち、その余勢を駆って藤原氏を滅ぼし、更にはまた範頼(のりより)殿も討ち果たされしとぞ。されば、もう鎌倉殿に弓引かんとする輩はただの一人とてあらじと思えど、そこは鎌倉殿じゃ。平家の残党狩りも九州、四国の山中を主に、今一段と厳しゅうならんと云う事じゃ」
頼景の話に、親重は己の背筋付近を走る悪寒を覚えた。何も雪の中を歩いて来て、風邪を引いた訳でもあるまい。顔色も一瞬の内に褪(さ)めた様にも思う。
ひとくさりの話を終えて、親重はそそくさと頼景の前を辞去した。外はまだ雪であった。館の軒先には、氷柱(つらら)さえ一尺ほども長く伸びている。
「急がねばならぬ」
家路を急ぐのではない。鶴の椎葉への逃避を急ぐのだ。
朝の往路では、数刻の後には納まるかに見えた雪であったが、復路ではまた一層激しく、南国には珍しい吹雪となっていた。その中を、前屈(まえかが)みになって身に纏った(まとった)蓑(みの)を強く抱き、笠の前の方を左手に摘(つま)んで荒ぶ(すさぶ)雪に抗いつつ先を急いだ。
その途上、それ以上の重さを支え兼ねたのであろう。雪を孕(はら)んで撓んで(たわんで)いた枝振りの良い松の一枝が、ドサッと云う鈍い音と共に彼の眼前へと落ちて来た。まるで鶴を含めた宮原家の、先の見えぬ前途を暗示するかの様でもあった。
九州地方としては やや遅い春が、どうやらこの求麻の山野にも廻ってきた。
「急がねばならぬ」
親重には、毎日そう思案しながらの久しく待ち望んだ春であった。
花々は待ち兼ねた様に一斉に開き、田畑には蓮華草を中心にした花々の蜜を求めて蜂がブンブン飛んでいる。
「鶴様は、また椎葉へお戻りになるげな」
「何でも椎葉家のお嬢様が病の後お亡くなりなさって、鶴様をまた返して欲しかと矢の催促ちゅう事じゃて」
春になって早々、行き会う村人達はひそひそと噂し合っていた。勿論、鶴にも親重にも、直に(じかに)尋ねる者など一人とていない。親重夫妻の近頃の憔悴(しょうすい)し切った様な顔を見る時、何人(なにびと)も一切の疑問は咽喉の奥に押し込めた儘にして、其処から先に引っ張り出すことには躊躇(ちゅうちょ)を覚えたのである。
村人に対しては、鶴は宮原家の遠縁椎葉家からの貰い児と云う事にしてあったので、再び椎葉に戻るらしいと云う噂になったのであった。
茂助は、今ではもう鶴の顔を見ようともしない。むしろ、何処か避けている様子でさえある。鶴が椎葉に行く様になった事、それすら茂助が知っているのか知らないでいるのか、彼女にはさっぱり判らなかった。
茂助の日焼けした顔付きも体も、もう精悍(せいかん)な大人そのものとなっていたが、その何処か怒ったような表情を見ると、鶴としてはとても声を掛け難い思いであった。父親の茂吉と共に、宮原家の裏手の粗末な小屋にも似た家から這い出て来ては、朝早くから夜遅くまで宮原家の田畑の耕作に勤しむ(いそしむ)のである。もう立派な一人前以上の働き手であった。
ある朝の事、手水場(ちょうずば)に立った鶴は、裏手で薪(まき)を割る茂助の姿を認めた。もう汗ばんでさえいる。何か声を掛けねばならぬ気がした。
「茂助……、さん」
今まで考えてもみない事であった。何時頃からの事か、当家の家人としか考えられなくなっていた茂助には、幼馴染の仲間意識からか、「……さん」などと改まって呼んだ事など一度もなかった事である。
不思議であったが、己の頬から耳の辺りまで焼け付くように熱くなった。
「はい」
ぶっきらぼうに答える茂助の眼は伏せられた儘である。
「朝早くから精が出る事……」
茂助からの答(いら)えはない。鶴の目の前では一尺(約30センチメートル)ばかりに伐(き)られた薪(まき)が、彼の手でいとも簡単に割られていく。その手に掛かると、本当に無造作に、自ず(おのず)から薪が割れていく感じであった。
鶴は続けた。もう、茂助が聞いていようといまいと一向構わない、己れ自身に言い聞かせる心算(つもり)でもあった。
「男(おのこ)に生まれなばよからまし。女子(おなご)は嫌じゃ。男にあらば、かかる憂き目もなかるべし。何時になれば、戦に泣く女子や子供のなくなるのであろう。茂助さん、教えて下され」
私はもう直(じき)此処から出て行って椎葉の人間になって仕舞うのだと、鶴は茂助に対し心の内で叫び、遠回しに訴えているのである。
茂助は顔を合わせようともしない。聞いているのかいないのか、相も変わらず薪を割っている。もう二山近くも割っているのにまだ続けるのかと、少々遣(や)り切れない気持ちにもなってきた。
もう往のう(いのう)かと鶴が考えた時、やっとの事、茂助はその重い口を開いた。表情は硬い儘である。
「知りませぬ。それはお父上様に伺うて下され。わしらただの百姓は、鶴様がお父上のお申し付け通りにする事じゃ。戦に従えと言われれば従いもする、畑を耕せと言われれば耕しもしもす。何ぞ、わしらに出来る事(こつ)があろうか」
冷たい返事であった。しかし同時に、全ての小作人の背負った宿命でもあった。
何故にこの世に分限者と貧者があるのか。なぜ地主は富み、一方で小作人は死ぬまで貧しい儘でいなければならぬのか、鶴には判らぬ事ばかりであった。
その日以来、鶴が茂助に声を掛ける事もなくなった。一方の他の村娘達も、あまりにも己たちと境遇の異なる鶴に、今では声を掛ける者も殆んどいない。
こうしていよいよ、鶴の出立する時期が近付いた。山野の草木は益々青く、花々の蕾は残らず膨らみ、水も温(ぬる)む晩春の頃となっていた。