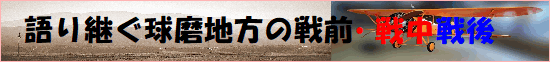
私の沖縄戦争体験 池原 喜忠(名城大学 元理事)
私は、沖縄県北谷町(ちゃたんちょう、中日ドラゴンズのキャンプ地)に生まれ、小学校(当時は国民学校と称していました)1年の時、沖縄戦に合いました。
1945年3月23日以降米軍の上陸地点となり、村は艦砲射撃の攻撃で家屋は焼失しました。当時家族は、長男が石部隊(いしぶたい、独立歩兵隊)に徴兵され、父が防衛隊(地域防衛の現地在住の男性により組織された軍事集団)、次男は護郷隊(ごきょうたい、戦争末期の1944年(昭和19)沖縄北部で組織された少年兵部隊(ゲリラ部隊)として召集されていました。
1944年10月10日、村の近くにある屋良飛行場が米軍の空襲を受けたのか黒煙が見えました。
戦争が激しくなるにつれて軍の司令部は、子供達を本土に疎開をということを考え、船(対馬丸6754トン)での疎開を試みました。学童の乗った対馬丸は、1944年8月22日に米潜水艦の魚雷攻撃受けて沈没したことは皆さん周知のことです。779人の学童を含む1476人が犠牲になりました。
一方、県内では、北部への疎開となり、北谷村の疎開先は北部の国頭村(くにがみそん)の羽地(はねじ)に指定されていました。家族が一緒に行動すると一家全滅となってしまうということで、家族が分散する形となり、祖母と叔父さん達に連れられて疎開しました。
疎開先での生活は大変でした。家族とは別の地域に居て、地域の援助(方言:ゆいまーる)もあって不便を感じながらも生活は出来ました。しかし母達のところは厳しく、聞くと、持参した食料も底をつき、三食から二食、一食と苦しくなり、ソテツ、ふき、かずらまで食べて飢えを凌いだとのことでした。栄養失調で無くなる人もいました。
1945年8月15日の終戦は疎開先で迎えました。宜野座村(ぎのざそん)のテント村に収容され、米軍の恵みよって生活していました。父は、島尻喜屋武岬(しまじりきゃんみさき)で捕虜になり、屋我地(やがじ)に収容され、ハワイに移送されました。長男は司令部のあった首里で戦死、次男は室川(方言:むるかー)の小屋で再会、五男は、母におんぶされ疎開途中に米兵の襲撃にあい、流れ弾に当たり即死しました。
家族が再会出来たのは1946年(昭和21)の夏、故郷の北谷村桃原(ちゃたんちょうとうばる)での生活にたどり着くには時間がかかりました。
戦後の私 尾家 亮(あさぎり関西会相談役)
去る 8 月は戦後 80 年の記念すべき年月でありました。昭和 20 年 8 月 15 日、私は国民学校の2年生でありました。
近所の母親たちがラジオの周りに集まって、天皇陛下の「終戦の詔書」(しゅうせんのしょうしょ)を聞くためでありましたが、電波の具合が悪く、殆ど聞き取れなかったようであります。
それまでの生活も大変厳しいものでありましたが、父親(当然、出兵中)の居ない女子供5人の生活は一段と厳しくなったものと思います。
食べるものがないのに、母親はどうして子供たちに食べさせてくれたのか全く理解できていません。しかし兄弟皆大きくなっていることを思えば、母親は1人子供成長のため必死に頑張ったのは間違いありません。
それまで町中にいたのに気が付けば突然田舎の納屋で生活していました。学校には1~2分の住まいから徒歩で30 分くらいの所に引越していました。麦だけの御飯は良い方、それからは麦の中にサツマイモが入り、おかずは梅干し1ケという内容。白飯の中に梅干し 1ケなら日の丸弁当でカッコいいのですが、サツマイモ(カライモ)の中に梅干しは、何というのでしょうか。
食べ物に困っていますので、食べられるものは何でもチャレンジしました。近くの小川で小魚をとったり、秋には稲に飛来する「イナゴ」をとり、炒めて食したり、山ではキノコ、野草など食べられるものは何でもチャレンジしたものであります。
着るもの、履くものも全くなく、同じシャツを洗濯することなく毎日着ているものですから「シラミ」がわき、学校で時々DDTの噴射がありました。履くものはありませんので、毎日「ハダシ」です。その後「わらじ」の作り方を教わり自分で作った「ワラジ」を愛用したものです。
その後、父親が復員してきましたので、生活は大分楽になったのは確かです。
このようにして自然と大きくなり、いつの間にか中学生となりました。しかし生活の質はあまり変わりなく貧しく厳しい時代でありました。
小・中学校と殆ど勉強した記憶がなく、よくぞ高校・大学まで行けたものだと感じている次第です。現在の小学生でも知っている英語は全く分からず、単語を少し覚えたほどで、高校に入ってから本格的な英語の授業が始まり、ついて行くのに必死でした。当然、塾などはありませんからその分遅れていたことは事実です。
そんな学校生活ですが落ちこぼれは一人もなく皆、高校に進学したり、中卒後、集団就職でそれぞれの生活の始まりであります。
そのような環境の中にあっても、皆、真面目に生活し、苦しくても人の物を盗んだり、他人を殺めたりする人は全くなく、私宅などいつも留守でも鍵をかけることはない出入り自由でありました。
それだけ貧しくともお互いに信頼しあって生きていく、素晴らしい生活空間であったと信じています。
昨今はどこに行っても世情不安でありますが、尊属殺人は当たり前、金のためならどんな極悪なことでも実行していく全く人間の心を持たぬ野獣と同じ人間の出現は悲しいことです。
昔のように貧しくともお互い助け合って生活していけるような社会になってほしいと願っています。
人吉の戦後・微かな記憶 金子 千津子(80歳・岐阜県在住)
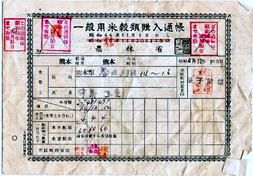 |
前略、どうにか関西会のホームページに辿り着き拝読させて貰いました。 人吉の近くに飛行場があり、身近にいろいろな出来事があったなんて、私は疎くて知りませんでした。ただ、回覧板のことは覚えがあり、米などは通帳もって買いにいったこと、味噌や醤油などは隣同士で物々交換したことなど、その経験はあります。 |
♪隣組は、隣同士が助け合う共助精神の高揚が叫ばれ、当時の人間関係はよかったと思っていました。しかし、国や軍の魂胆は隣組を組織化して戦争体制づくりをすることにあったんですね。
小学校の給食で出された脱脂粉乳は不味くて飲めませんでした!わが家では、人吉市の少し郊外の赤池あたりに、塩物の魚を持って行き、米と交換するなどして、一時期、闇米屋として生計を立てていたことなどを思い出しました。
米は、近所の知り合いの方達に売ったりして利ザヤを稼いでいました。間違いなく違法行為でした。戦中戦後というより、私の時代はもはや戦後の貧乏な中をどうやって生き抜くのかの時代でした。親たちが大変だったと思います。
私は姉妹5人、女ばかりの末っ子、何も知らず甘えん坊、わがまま娘で球磨の歴史など知らずに育ちました。この度の語り継ぐべき戦中戦後の体験・記憶は地元の財産資料として貴重です。残して欲しいです。後略