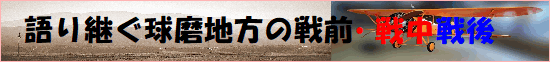
語り継ぐ球磨地方の戦前・戦中戦後 杉下 潤二(昭11年生・89歳)
はじめに
私は、岡原小学校の創立150周年記念講演で球磨地方の歴史を語ったのですが、その中で高原飛行場が爆撃され、神殿原飛行場の飛行機が油をかけて燃やされたこと、岡原小学校に軍隊が駐屯していて教室や運動場が占拠された時期があったことなどです。しかし低学年の小学生は退屈な話だったらしく、先生が席に出向いて静かに聞くように注意されていました。
戦中戦後の苦難を語ることは大変です。それは、特に戦中の困難を体験的に語り継ぐことのできる方が年齢的に少なっていくからです。球磨地方は空襲によって大都会のように居住地が壊滅するほどの被害はありませんでしたが、戦争のために、敗戦のために味わった苦難は多々あります。おぼろげですが、私の幼少時体験と記憶を基に幾つかを語り継ぎたい事項を紹介したいと思います。どうか皆さんも語り継ぐべきことをご教示ください。
<戦前>
戦前と言えば昭和15年以前、私が4歳頃より前ですから体験的に語り継ぐような事項の記憶はありません。私が生まれた年、昭和11年、1936年には226事件、皇道派の陸軍によるクーデターがあったようです。また、その4年前の昭和7年(1932)にも515事件が起きています。このような事件の記憶があるわけはないのですが、軍人や軍部の暴走の前兆が顕著になってきた時代であります。
太平洋戦争の要因は、時の日本が西欧による東アジア植民地支配をなくし大東亜共栄圏構想を打ち立てたことにあると思います。しかし、もっと遡れば吉田松陰の思想や明治維新の尊王攘夷にあります。植民地支配の敵を抹殺するために軍拡し、尊王を御旗に軍部の独走を容認したためであります。今度の参議院選挙では似たような政策を唱え、若者に支持によって大躍進した政党がありました。大丈夫でしょうか、少し不安です。
私が4歳の頃の思い出は、直接、戦争とは関わり合いないのですが紹介しましょう。多良木町黒肥地に競馬場(草競馬場)があり、わが家の農耕馬も出走することがありました。わが家の農耕馬は、大会で優勝したことがあるらしく、風呂敷くらい大きさの優勝旗がありました。その旗を持って、父親に連れられ応援に行ったことがあります。馬と戦争の関わりですが、この競馬は農耕馬が競うものですが、農耕馬がであっても戦場では軍用馬としてお役にたてるんだと父からしょっちゅう聞かされていました。草競馬場は確か、多良木の恵比寿さん前の道を黒肥地の方向に向かった球磨川の近くにあったと記憶しています。
1、隣組 回覧板
戦前から戦中、戦後も唄われた珍しい歌です。
♪とんとん とんからりと 隣組 格子(こうし)を開ければ 顔なじみ
廻して頂戴 回覧板 知らせられたり 知らせたり
♪とんとん とんからりと 隣組 あれこれ面倒 味噌醤油
御飯の炊き方 垣根越し 教えられたり 教えたり
♪とんとん とんからりと 隣組 地震や雷 火事どろぼう
互いに役立つ 用心棒 助けられたり 助けたり
♪とんとん とんからりと 隣組 何軒あろうと 一所帯
こころは一つの 屋根の月 纏(まと)められたり 纏めたり
隣組
・・この歌がラジオから流れていた覚えがあります。
現在ではネットや動画で、聞くことが出来ます。
私は、あまりにも調子のい歌だしコミカルなので、子供の頃に自然に覚えました。
この歌の狙いは、国民を組織化し戦争に協力する「新体制運動」大政翼賛会(たいせいよくさんかい)の一環であり、住んでいる町内の隣組まで組織化して戦争体制作りを始めた頃の歌です。ぜひ聞いてみてください。
<戦中>
1、出征兵士の見送り
♪わが大君に召さるたる・・・♪いざ征け つわもの 日本男児
どこそこの方が出征されるとの知らせあると、出征兵士やその親族達と行列を組み、手に小旗を持たされ、岡原と免田の境界、斎堂の先の並木通りまで行き、小学生はそこで最後の万歳をして兵士を見送るのが常でした。親族は免田駅まで行き車窓越しに、我が子、我が夫と永の別れをされたと聞きましたが、子供心に出征兵士を送る歌は勇ましく、親族の不安や悲しみは全く感じとることはありませんでした。幼小ながら戦時色に染まり、もう洗脳されていたのですかね?
2、高原飛行場空襲
 |
危ないから中に入れ!という父の声を無視して、私は防空壕から出て高原の飛行場に黒い煙が立ち上るのを見ていました。高原は文字通り高台にあるため、黒煙は球磨郡のどこからでも見えたはずです。 |
写真は、錦ひみつ基地ミュージアムに復元展示されている実物大の複座練習機・赤とんぼ。木の骨格に帆布が貼られています。
3、松根掘り勤労奉仕
松根油が飛行機の燃料になるとの情報を軍が鵜呑みしたことによって、国は松根油の生産を国策として発動し、学校児童も松根掘りに動員されました。岡原村での採取場所は黒原山だったと思います。松の切株を掘り起こしてどこかへ運びました。霧島神社の近くに松根油をとるための乾留所がありましたので、多分、松根はそこへ運んだのだと思います。錦町にはいまも松根の乾留跡が保存されています。
4、カラムシ(ラミー)や桑の皮むき奉仕
カラムシとかラミーというのは麻の一種です。このカラムシや桑の幹の皮むきの奉仕作業がありました。まず、カラムシという麻の一種は、今日でも道端で見かけますが、背丈が1m以上位、葉は細長いハート形をしていて、葉の裏は白っぽいです。幹の皮をむいて製糸し、布地とするのですが、布地は吸湿性がよく速乾性もあって高級な天然繊維でありました。麻布は弥生時代から貫頭衣の素材でもあり、今日でも、清め祓い神事で用いられる御幣の麻紐や緒(お)、神職の夏用衣は麻布であり、いずれも神聖な繊維や布とされています。
カラムシの皮むきは楽しみなどありませんでしたが、養蚕農家に出向いて桑の幹の皮むき作業は楽しみがありました。それは桑の実が食べ放題だからです。大人が切り出してくれた桑の枝には、実って黒くなった桑の実がびっしりでした。みんな唇を紫色に染めて笑いあいました。子供のころ、この桑の皮は何に使うのか聞いても誰も知らず、分からずままでした。大人になって中国の資料をあさっていたとき、偶然、桑の皮で紙を作ったという資料がありました。しかし、そのころの日本では何に使われたものなのか、今日のネットには漢方薬としての桑白皮が宣伝されています。往時の用途もそうだったのか分かりません。先の松根掘りと桑の皮むき奉仕は、いずれも学徒動員令に基づくもので、確か私が国民学校1年生の頃でした。学徒動員は中等学校以上のはずでしたが、戦況が厳しくなり、小学生も勤労動員されるようになっていたのです。
5、岡原小学校の駐屯兵
岡原小学校に軍隊が駐屯し、運動場に藁人形を立てて軍刀で切り裂き、また円錐濠を掘って、その周りをぐるぐる回って、何回廻っても目が回らないようにするための訓練、それは空中戦のためただと聞きました。兵隊さん達は時には往還(おうかん)に出て行軍をしていました。昔の鍛冶屋さんの近くの道端に休憩場が設けてあり、そこでは住民が炊き出しをして応対していました。食べ物は豚が食べるような粗末な雑炊だったように記憶があります。
6、分校授業
岡原小学校に軍隊が駐屯していて教室も校庭も占拠されていましたから、授業は村のお寺や神社及び集会場が分校となっていました。岡原村の竹野地区は「浄光院」という廃寺で、地区の集会場でした。分教場に先生が常駐されていたわけでなく、時々見回りにこられる程度でした。したがって寺で勉強した、させられた記憶はなく、寺は遊び場、今でいう放課後の学童保育施設のようなものでした。
7、米の供出
「供出」とは、物資を公共のために義務的に差し出すことです。昭和15年(1940)に農林省令「米穀管理規則」の公布により、生産者である農家に対して、一定数量の自家保有米を除き、残る全ての米を決められた値段で国に売る義務が課せられました。 これが“米の供出”です。政府は供出米を増やすため 農家に隠匿米がないか、竹槍で天井を突き刺すなど、まるで泥棒のように徹底的に探索しました。農家は自分たちの食べ物くらいは確保したいわけで、どこに隠す思案したわけです。わが家の隠し場所が見つからないか、はらはらしながら役人の捜索を見守りましたが、小さな胸は破裂しそうだったことを覚えています。供出物資は米だけではなく、寺の鐘や金属類も供出の対象でした。
<戦後>
1、神殿原での飛行機の焼却
 |
昭和21年、私が9歳か10歳の頃です。ある日、神殿原飛行場方面に黒い煙が立ち上り、私の集落(竹野)方面にも流れてきました。何事か聞くと、飛行場で飛行機に油をかけて燃やしているとのことでした。一昼夜たって飛行場に行ってみると、飛行機は形をとどめず黒い残骸となっていました。 |
神殿原飛行場の滑走路は、もちろん芝、というより雑草の生えた不整地滑走路でしたが終戦後も暫く放置され、雑草は背丈ほどに伸びていました。私が小学校4年生の頃、この滑走路までの遠足があり、草茫々の滑走路では余興として宝さがしがありました。宝さがしとは、先生が滑走路の草むらの中に、子供の喜びそうな駄菓子とか鉛筆とかノートを隠しておき、それを生徒が見つて「あったー!」と手をあげる催しでした。
何十年かぶりに尋ねたことがあるのですが、神殿原飛行場はどのあたりだったか、わが家のカライモ畑もまったく見当がつかず、まわりは黒ボク土の田園が広がり、昔の面影はありませんでした。
👆写真クリックで神殿原飛行場跡地図に拡大します。
(出典:あさぎり町文化財調査報告書第4集:2017.3熊本県球磨郡あさぎり町陸軍人吉秘匿飛行場跡)
2、食糧難
農家であっても、戦後は食糧難の時代でした。最も困窮されたのは非農家の家庭で、復員の方や非農家の方が米を分けてほしい、これこれと交換して欲しいといってわが家にも毎日のように訪ねてこられました。私が小学校3年生ころのカバンは復員兵の方が米と換えてもらうために持って来られたショルダーバッグでした。誰も持っていないしゃれたバッグで、私は得意でした。
球磨地方は海や港から遠く、親戚だった魚屋にも無塩(ぶえん)の魚はめったになく、辛い塩鯨か塩魚ばかりでした。母は百太郎の水嵩が減り、川藻が顔を出すくらいになると川エビすくいにショケもって出かけていました。
戦中戦後は兎の飼養が国策となりました。主たる目的は輸出のための兎の毛皮ですが食肉用としても飼育されました。筆者も兎を飼っていました。小学校では兎狩りが学校行事としてありました。生徒は竹棒をもち、山の麓で一列に並び山頂めがけて声出しながら兎を追い上げるのです。後ろ足の長い兎は、下り坂は苦手でも、登りが得意だからです。山の頂上では先生や父兄が網を張って待ち構えていました。捕まえた兎は大人達が食べたそうですが、今の時代では考えられないような学校行事がありました。
屠殺(とさつ)とは、食肉や皮革とするため牛や豚など家畜を殺すことです。密かに殺すのが蜜殺です。戦後の食糧難の時代、森の中で家畜の密殺も行われました。豚は型枠に入れられ川に投げ込まれました。食肉、タンパク源とされたのです。屠殺の現場は、子供は見ないよう大人に制されるのですが、見たくなるもので、陰に隠れて高鳴る心臓を抑えながら見たことがあります。
3、脱脂粉乳・粉ミルク
私が中学校1年か2年生の頃、昭和24年か25年頃です。ユニセフかGHQの企画なのかわかりませんが、食糧支援物資として脱脂粉乳・粉ミルクがドラム缶に入った状態で岡原中学校にも届きました。ドラム缶は蓋が緩められていて用務員室の土間に置かれていました。当時、用務員室とは言わず小使い室と言っていましたが、私はそこの小使いさんと親しく、休み時間には、ドラム缶に手を突っ込んで、固まった脱脂粉乳(粉ミルク)を取り出してかじっていました。ただ、この脱脂粉乳が今の学校給食のように牛乳として出されたことはありませんでした。多分、癖のある脱脂粉乳をミルクとして生徒に出すレシピが分からなかったからではないかと想像できます。
4、復員
母の弟は3人、うち二人が海軍で、南方で戦死しました。一人がシベリヤに抑留され、終戦後3年位たってから生還してきました。極寒の地からなぜ生きて帰れたのか、叔父が話してくれたことがあります。それは蹄鉄の仕事ができたからだとのことでした。招集前にやっていた集落での蹄鉄仕事が役立ち、芸(技)が身を助けたとのことでした。蹄鉄のためには火力が必要で、作業場の火力によって厳寒のシベリヤでもしのげたのです。おじの復員の日のおばあさんの喜ぶ顔を今でも覚えています。
夢にまでみた故郷を目の前にして無念の最後を遂げられた復員兵がおられます。肥薩線の列車退行事故による犠牲者です。復員兵満載の肥薩線の蒸気機関車が急坂トンネル内で止まってしまい、逆走したことによる轢死(れきし)や窒息死された50有余の復員兵の方です。この事件は球磨地方最大の戦争悲劇ではなかったかといま思います。詳細はヨケマン談義6でも紹介しました、ご参照ください。