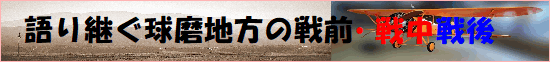
① 前略・・いろんな話、ありがとうございます。朝ドラの「アンパン」を見ながら、戦時中の話を、爺しゃんや父ちゃんにもっと聞いておけばよかったと、しきりに思います。父は速記ができ、テレビの記事を書いてくれて、教えてくれたのを懐かしく思い出します(8/28中部会K/F73歳)
② 前略・・戦時中の思い出、空襲警報がでると、近所の皆さんと防空壕へ駆け込んだこと、小学1年だった私たちは入学式もなく分散教育、近くの公会堂でした。もちろん机も椅子もないところで授業を受けました。暫くして戦争が終わり、二学期より学校での授業が始まり、一年生がたくさんいることを初めて知りました。
唯一残念なのは小学一年の入学式写真がないことでした。それから、苦労を共にした同級生が大阪に9人いたのですが、今では4人、87歳を迎えた今では会うこともままならず残念の一言です。貧しくとも元気なあの頃を懐かしく偲んでおります。後略・(8/28関西会IYさん87歳)
③ 読ませてもらいました。岡原の戦中歴史が、そうだったのか、です。同級生にも読んでみるよう伝えます。後略・・(8/28関西会SHさん85歳)
④ 前略・・私のうちは、神殿原飛行場跡ではラッキョウを作っていまして、その皮むきをさせられた思い出があります。娘が戦中戦後の話を聞きたいと申しています。その切はよろしくお願いします。娘の名は〇〇・・と申します。後略・・(8/28 球磨郡TSさん72歳)
⑤ 前略・・本日、父に送ってくださったメールを拝見してお話を伺いたく思いました。私は岡原で生まれ育ち、今は福岡におりますが、20年ほど前に亡くなった祖父の戦時中のことを調べているうち、人吉球磨や岡原の歴史にも興味を持つようになりました。一度お会いして詳しいお話を伺いたく存じます。どうぞ宜しくお願いいたします。(8/28福岡在住SKさん(④TSさんの娘さん)
⑥ 前略・・私の父も戦争に行っていますので戦中戦後が気になります。でも、関西会のホームページたどり着いてもなかなか「球磨地方」コラムが見つかりません。教えてください!後略・・(8/29中部会ISさん75歳)
 |
⑦ 免田町吉井の219号線沿いに親戚が有りおばあさんが住んでいました。中学時代に家から2km程をリヤカーを引いてからいも掘りに行った先が、神殿原飛行場の滑走路だった場所とのこと。と言われても、ピンと来なかった。だって、コンクリートのかけらが見当たらない。 |
拡大写真の上端の赤ぽつが親戚の家、上側の青筋は井口川、左下の青筋は免田川
(出典:あさぎり町文化財調査報告書第4集:2017.3熊本県球磨郡あさぎり町陸軍人吉秘匿飛行場跡)
⑧ 隣組 回覧板、今は唄う人はいませんが、私の町内では今も回覧板が回っています。
お宮さんの掃除、役場や市役所、福祉や町づくり協議会、老人会、自治会等からの案内や
お知らせ等々です。拡声器による放送もありましたが聞き取りにくく緊急時以外はなくなりました。みなさんの住まわれる町内では、自治体等からのお知らせはどんな方法ですか?
お知らせください。(9/1中部会 SJさん89歳)
⑨ コラム読ませて頂きました。子供の頃の様子を良く覚えておられるのでびっくりしました。怖い時代の事なので、多分一つ一つが記憶に残っておられるのでしょうね。私は戦後生まれで、怖い目をしていないので、子供の頃の記憶は朧気ながらでしか残っていませんが、知覧の特攻会館を訪れると(知覧の隣町に会社があることから、3度ほど行きました)、改めて戦争の悲惨さ、二度と起こしてはならないことを痛感します。
余談ですが、戦争で無くなった人の写真から、最新の技術によって動画に編集したものを、先日TVでやっていました。生きた姿のままに動きます。恐ろしい技術ですが、果たしてこれがこれでいいかは適材適所だと思います。
「隣組」の歌は知っています。今も歌うことは出来ます。きっと、テレビかラジオで流れていたのを覚えたのだと思います。回覧板ですが、私の地域では、「自治会」(市の組織)があって、役員、組長、班長、会員というようになっています。月の頭に組長会議があって、その時に回覧物があれば、組長 ⇒班長 ⇒一般家庭と回ってきます。組長、班長は1年ごとの輪番制(1組×5班×東・西あります。地域全体では9組まであります)です。組長となると結構やることがあるので、当番年になると引き受け手を探すのに苦労します。(班脱退の原因にもなっています)これとは別に「広報おおぶ」というのがあって、月1回市から配布員によって配布されてきます。(9/1 OTさん78歳)
⑩ 前略・語り継ぐ球磨地方の戦前・戦中・戦後”を読ませてもらいました。
松根堀リ、桑の皮むき奉仕に、小学生までもが動員されたこと、驚きました。食糧難・脱脂粉乳については戦後しばらく続いて、自分も学校給食で飲んだ覚えがあります。これを読んで朝ドラの”あんぱんまん”の話を思い出し、またこれの話を読んで、戦争は、絶対やってはいけないと強く思いました。
隣近所の情報は町内会の回覧板と市からの「広報さかど」等です。また時々市内放送で迷子、詐欺電話等のお知らせがあります。昔から余り変わっていません。後略(9/1 TKさん78歳)
⑪ 前略、投稿はプリントして拝読しました。戦前、戦時及び戦後のさまざまな状況が偲ばれます。
文面では、やはり「赤トンボ」と「神殿原飛行場」です。同飛行場は、400m尺度表示で記されていますので、滑走路の長さは、地図写真の白線枠から約1500mと推定されます。「赤トンボ」の離着陸には十分の長さです。
あと、小川龍二氏執筆の「悔恨」も読ませて頂きました。戦地戦場のリアル、就中(なかんずく)、斬首刑描写は鬼気迫るものです。後略(9/2 MHさん 86歳)
⑫ 前略、戦中戦後の語り継ぎ提案、いいですね。私の方も、愛知の沖縄調査会で愛知県における沖縄県人(県人会、青年会、学生会)が祖国復帰にどう関わってきたかを調査し、「愛知の中における沖縄県人の足跡を求めて 祖国復帰を顧みる VOL.4」としてまとめる活動をしています。先生の提案に近い形でまとまるのではないかと思います。
私はかって名古屋市立大学の阪井芳貴名誉教授の授業で「戦争体験」を話したことがあります。その時のレジュメを参考に添付しました。後略(9/2 YIさん 89歳)
⑬ 池原様の「沖縄戦争体験」拝読させていただきました。45年3月、米軍上陸と同時に早々と戦闘が開始され、もちろんこれも米軍の思うがままの一方的な戦闘であったと思われます。この当時の沖縄本島はまだ戦闘にまでは至ってなくて、臨戦態勢を整えつつある頃であった事でしょう。しかし、沖縄諸島では住民は逃げ惑うばかり、池原様宅のような悲劇も多数生じたものと思われます。
老いも若きも○○部隊、○×隊などと戦争に参加させられる無謀さ、ひいては対馬丸の惨劇にいたっては、やはり軍部に対して怒りさえ覚えます。
当然戦争は当人の周辺にとっても多大な迷惑や戸惑いを与えるものですね。池原様宅に於かれても数名の肉親の戦死、兵士ではなく一般国民であっても戦時中の死は{戦士}ではないでしょうか。
現在の日本国政府の一般国民に対する態度、「軍人や軍属ではないから補償はない」との態度にはどこかやり切れなさを覚えます。(9/5福岡県 RОさん80歳)
⑭「語り継ぐ球磨地方の戦前・戦中戦後を読ませていただきました。小学校で講演されたということですが、今年は戦後80年なので、戦争をどのように語り継ぐべきかというテーマでの記事が多かったようですね。若い世代にはこのような戦争について語り継ぐ記事を是非読んでもらいたいと思います。NHKの朝ドラ、「アンパン」も見てほしいですね。
私は昭和17年生まれなので、杉下先生よりもさらに戦中・戦後を語る記憶がありません。ただ、私は満州生まれの引揚者なので、母が叔母と共に6歳(兄)、4歳(私)。3歳(弟)の3人を連れて帰るのは大変な苦労をしたと思うのですが、残念ながら引き揚げの記憶もほとんでありません。ただ、私の家には大東亞戦史という本があり、高校生の時に満州引揚者の記録を読みましたので、特に開拓団の方々が大変な苦労をされたことは認識しています。幸いにして、父が満州鉄道に勤務していたことから、多分引き揚げる際に多少の便宜が図られたものと思っています。
父は終戦前に召集されたのですが、けがをしたのが幸いしてソ連への抑留はされずに帰国できました。両親には満州での生活や引き揚げの苦労話を聞いたことはありませんが、両親も語りたくなかったのでしょう。
杉下先生の記事にあります回覧板の歌は私も覚えていますが、戦後の記憶であると思いますし、桑の実は育ち盛りの小学校時代に食べたことがありますが、親にはひどく叱られました。食べたことは口の中の証拠を隠しようがありませんので。
世界では民主主義国家は30%を切っており、民主国家の旗手としての米国が、トランプという大統領による独裁国家に、簡単に変身するのを見せつけられ、ヨーロッパでも右よりの政党が台頭しているのを見ると、日本も大丈夫かなと思ってしまいます。特に今回の参議院議員選挙では新しい政党が躍進していますので、世界の政治的な動向に大いに気になるところです。
どちらにしても戦争の記憶は語り継がれるべきだと思いますが、80年が区切りになってしまうことを危惧します。(9/7 AHさん83歳)
⑮ (前略)「私は2歳のとき終戦をむかえました。あまり記憶は定かではありませんが、当時、薄いピンクの防空頭巾を持ち歩いていました。幼稚園にも持っていきました。そんなことしか覚えていないんです。(中略)
ただ小学校に上がったころ、近くに外人さん(多分アメリカ人)、が開いていた日曜学校があり、何も分からず通いました。どうもキリスト教の布教活動だったと思います。カトリックかプロテスタントかも分からず出ていました。初めて外人さんを見たのはそこでです。でもお陰様で、マタイ伝からヘブライ伝までキリスト教の順番は薄っすらと今でも覚えています。(後略)(9/8 人吉出身、岐阜県在住、KTさん80歳女性)
⑯ 今「語り継ぐ球磨地方の戦前・戦中・戦後」を見ていますよ!懐かしいですねぇ!ありがとうございます❗(9/29 上出身KNさん、83歳)